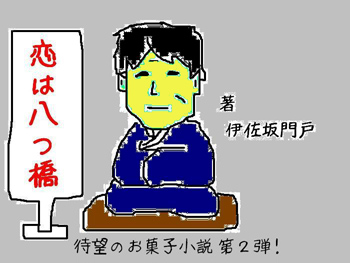
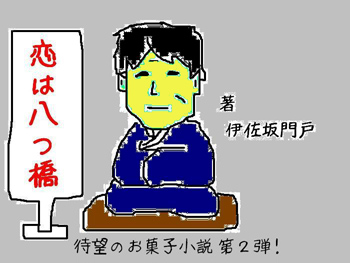
|
2月の京都は風が冷たい。 東京の風よりも冷たく感じる。 寒さに弱い私としてはどうもこの時期の京都は苦手だ。 それでも私は京都に来ている。 もちろん観光ではなく仕事だ。 今日は京都大学落語研究会が主催する「京の奇跡」というイベントで一席演るのだ。 ギャラは良くないが私はできるだけこの3ヶ月毎に行われるイベントに出るようにしている。 私にとってこのイベントでいつも作りたてのネタを演じて、 そのネタが使えるものかどうかを試す貴重な実験室だ。 ウケなくてもどうせ小さなイベントなので私の生活になんらマイナスを生じさせないのだ。 汚い考えなのかもしれないがこういう仕事をしている以上それは必要なことだと私は思っている。 最近は減ってきたが地方での公演が私の仕事の大部分を占めている。 私は決まって自分の出番まではその街々をぶらつくことにしている。 それはもちろん観光の意味合いもあるのだが、一番の意味は他の人のネタを観ないためである。 他人に影響されることで自分のオリジナリティを無くすことが怖いのだ。 「作る側」の人間にとってオリジナリティを無くすことは終わりを意味する。 考え過ぎなのかもしれないが私は影響されやすい方なので、 必要以上に他人のネタを観ることを避けている。 そのせいもあって私には同業者の友人というのがまったくもっていない。 今日も冷たい風に吹かれながら両手をポケットにつっこんで、 46歳の男は京都の街をぶらぶらと歩いているのだ。 どれくらい歩いたのだろう。 中心部からはだいぶ離れたところまで来てしまったようだ。 体も冷えてきたので喫茶店でも見つけて熱いコーヒーでも飲みたいところだが見当たらない。 見渡したところで店と呼べそうなものは小さな土産屋と昔ながらの日用雑貨店くらいだ。 しょうがないので私は小さな土産屋に入った。 客は私と若い男女が1組、たぶん恋人同士であろう。 そして、お決まりの京都の八つ橋が積まれている。 店内が狭いせいもあって男女の会話が聞こえてくる。 「やっぱり京都土産と言えば八つ橋だよなぁ。」 「そうよねぇ。」 「最近の八つ橋はいろんな種類が出ているんだね。」 確かに若い男の言うとおりに最近の八つ橋はいろんな種類がある。 このお店にもいちごあん、チョコレート、クリーム、桜あんなど様々な種類の八つ橋が置かれている。 「でも私は普通の八つ橋が良いなぁ」 若い女は続ける。 「だってあの和風の団子生地に一番合うのは、食べた後に上品な甘みを残すあんこだもん。」 全然理由にはなっていないのだが理解はできる。 私もたくさんある八つ橋の種類の中でやはり普通のあんこが入ったものを選ぶだろう。 私は一箱1000円の普通のあんこが入った生八つ橋を手に取り会計を済ませた。 そして、店から出ようとしたその時だ。 私の中で一つのアイデアが生まれた。 正確には光ってはいるがそのアイデアは生まれてはいない。 以前にあったような感覚だ。 そう、恋愛ネタで落語っぽい事が出来ないだろうかというアイデアが生まれた時だ。 あの時もこの感覚に近いモノがあった。 私は興奮を抑えつつ店を出て、マネージャーの吉田に電話した。 「今日の演目だが変更することにした。」 電話越しに吉田の驚く声が聞こえるが誰も今の私を止めることはできない。 私は説得を続けた。 吉田も私の性格を十分理解しているのでしばらくすると了承して、 関係者に説明してくれることになった。 電話が終わると私は小走りに街の中心部に向かい喫茶店を探した。 息がすぐに切れたがかまっちゃいない。 早く頭の中のアイデアを引っ張り出さなくては消えて無くなるかもしれない。 そうなっては一大事だ。 |